これから私が書き綴るエピソードは全て実話。本来ならばその名前も公表したいところだが、私自身が迷惑を被るだけかもしれないので、やむなく仮名を使用する。
尚、あまりにも古い記憶が多々あるので正確な日時まではさすがに思い出せないのでザックリとした表現になることがあることもご了承いただきたい。
更に、その【親】という肩書きの男とその嫁のことを幼少期から【おかしい】【絶対に普通じゃない】と見抜いていたので、もはや今更【お父さん】【お母さん】とは口が裂けても呼びたくないし、呼べない。仕方なく【父】【母】と表現するが、それすらも激しい抵抗感と嫌悪感に襲われることも考慮していただきたい。
本編
私の記憶の始めは、全体的にグリーンがかった色に包まれた空間の中にポツンと革製の茶色のベンチに腰掛け、俯いている小さな女の子がいた。
それはまだ小学低学年にしか見えない、幼少期の私だ。赤いスカートを履いている。表情までは見えないのだが、何やら寂しそうでもあり、暗い。そんなところで一体何を考え込んでるのか、もしくはただそこに待たされているだけなのか?それも読み取れない。
だが、その夢のような光景が意味していたものは私が小学5•6年に進級したあたりでわかるようになった。
そこは皮膚科のロビーだろう。私が自分で自分の髪や眉毛、まつ毛を抜いて、明らかに病気になっているため、【母】が皮膚科で塗り薬をもらうために私を通院させていたようだ。
【母】は毎日呪文でも唱えるように「あんた、その手袋を絶対に外しなさんなよ」と、幼い私に言い聞かせ、手袋を外したら体罰だ、というような顔付きをして言っていた。
【鬼】
あれはそう呼ぶに値する顔と声。
まだ物心がつかないうちから私の目に映っていたその顔は【鬼】。
「その手袋を絶対外すな」そういう台詞も【言い聞かせる】のではなく、幼い子供の私には恐ろしく強烈な【脅迫】でしかなかった。
「この手袋を外したら怒られる」と、わかりきっているのに、夜、布団の中に潜り込んで、堪えきれず手袋を外し、コッソリと、見つからないように、特にまつ毛を抜いていた。まつ毛を抜くと軽い痛みがある。でも、その軽い痛みが堪らなく快感で、私はその癖を抑えることができなかった。
ごくたまに、それが【母】に見つかり怒られた時は、もう怖くて恐ろしくて、口答えなど到底できるものではなかった。心の中で【目の前の鬼が怒っている】と、心底怯えながら、小さい体を一層縮こませて、その【悪鬼の形相】を自分の目に焼き付けていた。
これは後になってわかったことだが、その毛を抜くという行動、衝動は【抜毛症】という病気だった。
成人して結婚した直後に理由のわからない病的な症状に襲われ続け、ついには倒れて寝込むようになり、夜勤に行くはずの夫を休ませ「精神科を探してくれ!」と叱責するような感じで怒鳴りつけたことを今でも鮮明に覚えている。
謎の偏頭痛、ニキビ地獄、夫が仕事に行った直後に何故だか恐くて恐くてたまらず、泣きながら会社に電話して「帰って来て」と夫に懇願する日々が続いた。
「何がそんなに恐いんか?」
夫は怒りはしなかったが、その素朴な疑問を投げかけられた時、私は明確な答えを返すことができずにまた泣きながら「わからん!わからんけど恐くて恐くて仕方ないんよ!」半ば逆ギレみたいな台詞を吐いた。
内科や色んなところを検査してもらったが「特に異常なし」と言われるたびに落胆し、「それなら何でこんなに苦しい?何もないはずない!」と思い、もう残るは精神科しかない、と可能性を潰すためもあって精神科を探してもらい、夫に車でそこまで連れて行ってもらった。だが、その精神科はとんでもないドクハラ病院で「あんたは一体何が言いたいんか!」と、白髪頭の院長から怒鳴られた。
こんな病院、信じられるわけない。とりあえず安定剤だけを出してもらって、ちゃんと信用できる精神科を探して、偶然にも早めに見つかった。そして通院、カウンセリングが本格的に始まったが、その医師から私の本当の病名を言われた。
「あなたの病気は、境界型人格障害です」
私は、「何ですか?それ」と、初めて聞いた病名に驚くよりも?マークでいっぱいだった。
今の時代ならググればわかる。だからその病気の説明は割愛する。
そのうちに病気はどんどん悪化。あれだけタフがウリだった夫も日に日に弱っていくのが私にも見えた。
「旦那さんと別れて生活保護を受けるか、病院に入院するか、親元に帰るか、この三つの中から選びなさい」
ある日、医師から唐突にそう言われた。その医師にも見えていたのだろう。このままでは二人共揃って共倒れする、と。
私にとっては究極の選択だった。
旦那と分かれて生活保護?
精神科の病院に入院?
親元に帰る?
どれも地獄。特に「親元に帰る」だけは耐えられない地獄だ。
それでも、最終的に夫も会社に居づらくなったようで、会社を辞めることを考えていたらしい。
その際、医師から忠告を受けた。
「僕が知る限り、この地域であなたの病気を見れる医師は二人しかいない」と。
でも、その二人の医師は私が信用できる人ではなかったので、「もう、薬さえもらえれば自分はいいから、カウンセリングはあんたが受けて」と、まともに診てもらうことを辞めた。
それで、たまたま行った精神科で今の私の主治医に出会った。
【地獄に仏】
そんな表現では足りないくらい、その先生は私の病気に精通していて、カウンセリングも私自らができるほど、色んなことを知っていた。
その時のカウンセリングで、毛を抜く癖が幼少期にあったと言っただけで、先生はカルテに【抜毛症】と素早く書いたのが見えた。
「これが間違いなんですよ。その時代にも小児科のそれらしき病院なり施設はあったのに、あなたを皮膚科に連れて行った。もしもその時お母さんがあなたをそういうところに連れて行ってれば、ここまで酷くならなかったでしょうね」
そう先生はハッキリと【母】の犯した過ちの一つを私に教えてくれた。
私は私で考えていた。
「毛は私が自分で抜いてるのをわかってるクセに【皮膚科】に【手袋?】ありえんけどな!」
どう考えても納得できない。だが、当時の私にはその【母】のやらかした重大なミスを指摘したり、ましてや責めるなんて知恵も経験も説得力も何もなかった。ただ、成長するごとに【母】に対する不信感は増すばかりだった。
そうして、気の遠くなる刻を経てその先生と出会い、カウンセリングを続けていけばいくほど【親】が、特に【母】が憎くなり、奴らには怒りと殺意すら抱き続けることになる。
奴らを許すなどという選択肢は微塵もない。
なんの罪もないはずの幼い我が子が必死にSOSのサインを毛を抜いて訴えていたのに、バカな【親】は何一つ気付かず、的外れもいいところの処置しかしなかった、と先生も言って、私に一言、「辛かったですね】そう慰めのような言葉を投げかけてくれたので「やっとわかってくれる人が一人だけいた」
色んな感情が渦巻いて、私は泣き崩れた。
そうなるともう止まらない、【親】への憎悪と天にも届きそうな怒り、反発、あらゆる負の感情が私を支配していくのが自分でもわかった。




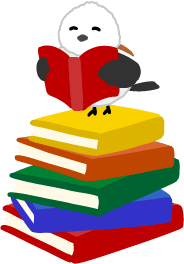

感想1
親への憎悪や反発、負の感情が湧き上がるのは無理もないことだと思いながら読みました。抜毛症に【皮膚科】と【手袋】は一つの象徴的なわかりやすい出来事だろうと思いますが、ここまでわかりやすくなくても、【親】による無理解や不適切な扱い、いろいろな出来事が日々あったのだろうと思いました。そもそも子どもが抜毛症になるに至るまでには相当なストレスがあったのだろうと思われます。自分でも何がつらいかわらなかったのかもしれませんし、自分が悪いと責めていたかもしれません。
医師が伝えてくれた「辛かったですね」という言葉はその通りだと思いました。それに加えて、私はそんな辛い状況にあってもあなたが自分の感性や気持ちを諦めずに自分の力で自分を守ってきたことに深い敬意を抱きます。「よくぞ、ここまで生き抜いてきましたね」と伝えたいです。
経験談には明確な怒りが書かれていました。怒りは自分に直接向けられていないものであっても、時にその力に圧倒されたり、ダメージを受けたり、受け止めきれずにしんどくなることがあります。しかし、私はあなたが書いた【親】への怒りはやみくもにぶつけられる感情とは違って、どこか自分を鎮めようとする力があると感じました。怒りというより、憤りに近いのかもしれません。かつて憤りには個人的な怒りに近い「私憤」と、自分の個人的な感情や事情を含めて、社会的な意味合いが含まれる「公憤」があると本で読んだことがあり、印象に残っているのですがそれを思い出しました。あなたの怒りや反発、憎悪などは単にあなた個人的な感情であるのではなく、社会にある理不尽さへの抵抗を含んでいるように思えたのです。あなたの経験談を読み【親】という個人の問題ではなく、【親】を生み出し、【親】に子どもの人生を丸投げする社会構造について思い至っています。あなたは「いや、そんなことはなく、【親】への憎悪や怒りを書き出したものです」というかもしれませんが、読んだ私にはそれだけではない何かを感じました。とはいっても、単に私が触発されて自分の中から自分の想いが引き出されただけかもしれません。いずれにしても、あなたが表現してくれた怒りのエネルギーが確かに私に届き、私をいい意味で揺さぶってくれました。
これからも今回のような発見があり、感情が動くことがあるかと思います。そのたびに自分の感情の扱いがわからなくなったり、疲れ果ててしまうこともあるかもしれません。それは無理もないことだろうと思います。ただ、そうした気づきは自分を理解し、受け止めるために必要なことだと私は思いました。私はあなたが明確に【親】へノーを突きつける力の存在を頼もしく思います。その感性を尊重したいです。これからも、表現したいことがあれば、いつでも来てください。